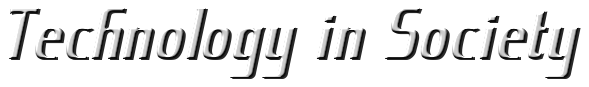広島大学A研究室では生体認証技術に係る研究を10年ほど継続して実施してきています。これまでに行ってきた理論上の検討及び要素技術研究を終え、今般実証研究に入ることとになりました。
さて、こうした研究を実施していく際に、ELSI的視点から具体的にどようなどのような検討を行ったらいいのでしょうか。研究の実施再度としては結構悩むところですよね。
ここでは、研究内容を仮想的に設定し、設定された研究に対しELSI的視点からの具体的な検討を試みます。
仮想した生体認証技術の実証研究
研究対象技術
実証の対象となる生体認証技術は多岐にわたるが、具体的には以下が研究対象となっています。
- 顔認証技術
- 光彩認証技術
- 声紋認証技術
- 指紋認証技術
- 掌毛細血管認証技術
いずれの認証技術も、現に全世界で様々に研究開発が行われ、既に広く社会実装がなされた技術も多々存在しています。A研究室ではこうした技術の現状を踏まえ、上記した様々な認証技術の評価を研究の目的としました。
研究内容
上記の生体認証技術を様々な条件下で使用し、それぞれの認証技術がどのような条件下で最も有効に機能するのかを、実証的に明らかにすることを研究の目的としました。
具体的には、認証の対象となる人々の属性を条件として設定し、上記1.~5.の生体認証技術が最も有効に機能する属性を明らかにします。条件として設定する属性は以下を想定することにしました。
- 人種
- 性別
- 年齢
- 健康状態
- 居住地域
この研究により、認証が求められる実際の状況において最も適切な認証技術の選択が可能となります。より具体的には、研究の成果として認証対象となる人間集団の属性に最適化された認証技術の提供が可能となります。
さらに、人間集団の属性に応じたモデファイを認証技術に行うことで、認証精度の向上が期待されます。結果として、生体認証技術の社会実装に大きく貢献することができるでしょう。
研究手法
本研究を実施する上では、1.~5.の属性を持つ人々の被験者としての協力が必要となります。このため、研究の第一段階としては研究に協力してくれる上記各属性の人々を被験者として募り、被験者の属性ごとに個々の認証技術の精度を測定します。
その際には、測定は非侵襲的であって健康には全く影響がないこと、得られたデータは匿名化し測定結果から個人が特定されることが無いことを説明する予定です。
その上で、被験者としての研究への協力、得られたデータの研究への利用、匿名化した上での結果の公開それぞれに関し、署名により同意を得ることとしました。
ELSI的視点からの検討
個別の研究に対する検討の前に
個別の研究内容に関して検討する前に、研究に対する様々な制約、研究に対する規制と言い換えてもいいかもしれませんが、この存在を認識することが必要です。
学問の自由は憲法で保障されているのでは、との反論もありそうですが、私は無制限の自由が保障されているとは考えていません。
この点をどう考えるかは非常に重要であり、また全ての研究に共通することから、投稿記事ではない一稿を起こしています。以下がリンクですので、是非内容を確認してください。
研究対象技術の研究の是非
A研究室で研究しているのは生体認証技術である。具体的な技術は研究対象技術として示された1.~5.であるり、これらは皆、既に社会に実装されています。
そうした現実の中で、その技術の利用の是非に係る議論が大きく存在していないのであれば、その限りにおいてこうした生体認証技術を研究の遡上に載せること自体に対するELSI的な視点からの検討の必要性は高くないでしょう。
それは、社会の判断として仮に1.~5.の認証技術の社会実装に何らかの問題があるとされているのであれば、技術の利用に対し何らかの異議が申し立てられていると考えられるからです。ただし、油断はできません。それは、あくまでも現時点での話だからです。
状況が変われば判断も変わる
状況は容易に変わり得ます。状況が変われば、判断もまた変える必要があります。
問題の有無の断の基礎となる社会の価値意識は常に変わり得ます。ポジティブに表現するのであれば、社会の価値意識は常に進化しています。昨日まで問題なしと判断していた価値意識が明日も同じとは限りません。
例えば、実装されていた生体認証技術の利用によって回復困難な被害が特定の個人に発生したとしましょう。こうした事案が広く報道されることで、社会全般に生体認証技術の利用に対する忌避感が広がったとしたら、どうでしょうか。
もちろん、これをもって研究を実施すべきではないとの結論には至りませんが、研究をより慎重に進める必要性は高まるでしょう。
新たな科学的知見が得られたら
もう一つの留意点は、新たな知見の獲得です。既に社会で実装されている技術であっても、科学的な知見の充実によって新たな知識が得られることは多々あるでしょう。
従来の知識に基づけば問題ないとされていた技術の利用が、新たな知見の獲得により突然問題ありと断ぜられる可能性は十分に存在します。
カネミ油症事件を過去事例解説として取り上げました。
事件は1960年代後半の発生でしたが、この事件もう少し後代に発生していたならば、PCBの製造事業者であった鐘ヶ淵化学工業に対する法的、社会的、そして倫理的な責任すべてにわたり、その問われ方は大きく異なったはずです。
ゲノムデータ利用の認証技術ならどうか
さらに、上記1.~5.の生体認証技術の研究を行うことが現時点において問題ないとしても、上記以外の生体認証技術であればどうでしょうか。
例えばヒトの全ゲノムを瞬時に読み取り(そうしたことが可能か否かはこの際考えません)、そのデータを事前に登録された当該人のゲノムデータと照合することによって認証を行うといった技術です。
こうした技術の社会実装は、私の直感では相当の社会的摩擦が予想されます。では研究だけならどうでしょうか。このような技術の研究は、将来的な社会実装を目指して実施されることが通例であり、おそらく慎重な姿勢が求められることになるのでは、と思います。
現在、作成中です。