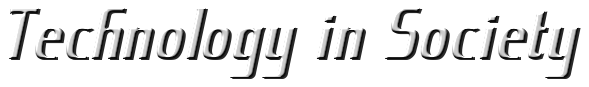カネミ油症事件に対するELSI的視点からの検討
1968年(昭和43年)、日本で発生した「カネミ油症事件」は、戦後最大級の食品公害の一つとされています。法的(Legal)、社会的(Social)、そして倫理的(Ethical)な視点から事件に関係した企業の責任が問われました。
もちろんこの当時、ELSIという言葉や概念が存在していたわけではありません。しかし、今日的な意味でのELSI的視点からの検討のあり方を考える上で、非常に参考となる事例となることから、ここで紹介することとします。
もちろん、関係した企業の諸「責任」の有無を判断する意図はありません。過去に実際に発生した事案を事実に基づいて紹介することで、ELSI的視点からの検討の糧にできればと考えています。
事件の概要
カネミ油症事件とは
1968年当時、北九州市に本社を置くカネミ倉庫が製造した米ぬか油に、熱媒体として使用されていたポリ塩化ビフェニル(PCB)や、その製造過程で生成したダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン)が非意図的に混入しました。
このPCBは、当時大手化学メーカーであった鐘ヶ淵化学工業(現・カネカ)が製造した製品を使用していたものです。この油が「食用油」として市場に流通し、多くの家庭で調理に使われた結果、全国で健康被害が発生しました。
主な症状と被害規模
被害者は油を摂取した直後から皮膚の異常(強いニキビ様発疹、色素沈着)、目や爪の変化、肝機能障害、免疫力低下、神経症状など多岐にわたる健康被害が現れました。母体から胎児への影響も深刻で、母体を通じた胎児汚染も確認されました。
公式に確認された患者数は約1,800人、摂取した可能性がある人々は数万人に上るとされています。事件は「PCBによる世界初の大規模食中毒事件」として国際的にも注目されました。
その後の対応と責任問題
国やカネミ倉庫による補償制度は設けられましたが、被害者救済は不十分で、裁判や認定基準をめぐる争いが続きました。PCB製造元である鐘ヶ淵化学の責任についても長く議論されましたが、法的責任の追及は限定的にとどまっています。
PCBの製造者に責任があるのか?
事件の直接の原因
カネミ倉庫が米ぬか油を製造する際に、加熱用の熱媒体としてPCB(鐘ヶ淵化学製)を使用していました。
加熱装置のトラブルなどにより、PCBやダイオキシン類が食用油に混入したことが直接の原因です。つまり「食品にPCBが混入した工程」はカネミ倉庫側の管理問題でした。
PCBの製造者の立場
PCBは当時「電気絶縁性が高く安定した物質」として広く利用されていましたが、毒性に関する知見は限られており、社会的にも「危険物質」との認識はまだ弱い時代でした。
鐘ヶ淵化学が製造・販売したPCBは、あくまで「工業用」であり、食品に使うことは想定されていませんでした。
そのため、裁判などでも「製造者が直接の法的責任を負う」とはされませんでした。
製造者の社会的責任は?
1970年代以降、PCBの毒性や環境残留性が国際的に問題視され、現在ではPCBの製造も使用も禁止されています。
現在では「危険性を十分に検証しないまま市場に供給した化学メーカーの社会的責任」は問われ続けています。
被害者や支援団体の中には「製造元にも説明義務・注意義務があった」と主張する声もあります。
製造者の責任に関しまとめると
法的責任(直接賠償責任)については、 主に油を製造・販売したカネミ倉庫が負うとされました。
社会的責任・倫理的責任については、PCBを供給した鐘ヶ淵化学(現カネカ)にも、化学物質の安全管理やリスク周知の点で一定の責任があると考える意見も存在します。
当時の状況下、倫理的責任を問えるのか
1960年代当時のPCBに関する知見と状況
PCBは1920年代から世界で製造・使用されており、1960年代には絶縁油・熱媒体などで「安定性が高く安全な工業用物質」と見なされていました。
一方で、皮膚障害(クロロアクネ)や肝障害などの毒性報告はすでに出ていました。特に1930年代から動物実験や労働者被害の報告が存在 していたのは事実です。
PCBは「工業用であり、食品や人体に触れる用途は想定外」でした。よって「米ぬか油製造装置にPCBを熱媒体として使う」こと自体が、本来は不適切な設計でした。
PCB加熱で生じるダイオキシン類(PCDF)の毒性については、当時ほとんど認識されていませんでした。
倫理的責任の評価
製造者(鐘ヶ淵化学)は「工業用PCB」を販売しただけであり、食品用途に供することは想定していませんでした。このため、裁判でも直接の法的責任は問われませんでした。
したがって「リスクがあることを明示すべきだった」、「使用範囲を明確に限定すべきだった」という 説明責任・予防的配慮の不足 は問えるとの判断はあり得るでしょう。
ただし、食品製造工程に誤用されるとは予見困難であったため、「倫理的にどこまで責任を負うべきか」は今なお議論の余地があると考えられます。
現代の視点から
今日の 予防原則(Precautionary Principle) の観点からすれば、以下の批判は成立し得るでしょう。
- 毒性報告がある物質を「安全確認が不十分なまま大量に市場供給した」こと自体に問題がある。
- 製造者は best available knowledge を踏まえ、リスクを十分に検証・警告すべきだった。
一方で、1960年代の科学水準と規制枠組み を考えると、当時の製造者に「現代レベルの予防原則」を求めるのは難しい、という反論も成り立ちます。
倫理的責任に関する議論をまとめると
要は、当時は科学的知見が限られており、製造者に法的責任は問えなかった。しかし既に毒性の兆候は知られていたため、説明責任を果たさなかった点で倫理的責任の議論は残る、ということではないかと思われます。
ただし、こうした見方はあくまでも現代の観点に則って考えた場合であることに留意してください。
社会的責任 – 大きな社会的圧力の下で
実は製造者は和解金を支払った
1968年に発覚したカネミ油症事件では、被害者たちがカネミ倉庫だけでなく、PCBの製造者である鐘ヶ淵化学および国を被告として提訴しました。
鐘ヶ淵化学は当初、法的責任を否定する立場をとっていましたが、最終的に一定の和解金を支払うことになります。
裁判での争い – 両者の主張
被害者らは、食用油の製造過程でPCBが熱媒体として使用され、そのPCBが配管などから漏れて油に混入したこと、さらには加熱過程でダイオキシン類等が生成されたことを主張しました。
鐘ヶ淵化学側は、PCBは工業用であり、食品用途での使用を想定していなかったこと、また毒性・混入の予見可能性について法的には認められないと主張しました。
1970~80年代にかけて原告ら(被害者)と鐘ヶ淵化学、国等との間で多数の訴訟が起こされました。福岡高等裁判所などでの控訴審では、鐘ヶ淵化学および国の責任を否定する判決が続きました。
最高裁による和解の求め
訴訟は最高裁にまで行きました。1986年(昭和61年)秋、最高裁は被害者側と鐘ヶ淵化学に対して和解の打診を始めます。
和解をしなければ、鐘ヶ淵化学および国の責任が否定される可能性(原告側が勝訴できない可能性)が高いとの見通しがありました。
1987年3月20日、全国統一民事原告団など原告側と鐘ヶ淵化学およびカネミ倉庫との間で和解が成立します。被告である鐘ヶ淵化学は「法的責任を認めるものではない」ことを条件に、和解金の支払いに応じました。
なぜ、製造者は和解を受け入れたのか
和解受け入れの背景は
もちろん、その当時の鐘ヶ淵化学がどのような思考経路を経て和解を受け入れるに至ったのか、その実際のところはわかりません。
当時の状況から受け入れの背景を推察すれば、図表1で示した四点にまとめられるのではないかと思われます。
| 裁判リスクの増大 | 長期訴訟での原告側の証拠提出等によって、鐘ヶ淵化学にも責任を認めざるを得ない可能性が高まっていました。そうした中、最高裁での判決が鐘ヶ淵化学・国の敗訴となる可能性も見え始めていたという見方も存在しました。 |
| 社会的・世論的圧力 | 被害の甚大さ、被害者の苦しみ、マスメディア報道などを通じて、責任を明確にすべきとの声が強まっていました。このため、企業イメージへの影響を回避したいという動機があったとも考えられます。 |
| 被害者の立場 | 被害者側は長期にわたり健康被害・生活の困難を抱えていたため、裁判の長期化よりも早期の解決を望む声がありました。和解によって一定の補償を得る道を選ぶことが被害者にとっても現実的だったともいえます。 |
| 最高裁による「和解打診」 | 判決による不確定性を鑑み、最高裁が和解への誘導をしたことは決定的であったと考えられます。判決によって被告側が全面的に責任を負う可能性があったため、和解が戦略的選択となりました。 |
「支払わざるを得ない」選択であった
鐘ヶ淵化学が和解金を支払ったのは、法的責任が確実に認められていたわけではないものの、裁判での敗訴リスク、社会的・倫理的圧力、被害者の救済を早めたいという実際的要請、そして最高裁による和解打診といった複数の要因が重なったためです。
和解は法的には責任の認定を含まないものの、企業の社会的役割・被害者救済の観点から、鐘ヶ淵化学にとって「支払わざるを得ない」選択であったと考えられます。
今日的視点からのELSI的含意
法的、社会的、倫理的責任の行方
本事件は、法的(Legal)、社会的(Social)、そして倫理的(Ethical)な視点から、PCBの製造者であった鐘ヶ淵化学の責任が問われました。
法的な責任に関しては、「法的責任を認めるものではない」ことを条件に和解に応じたわけですから、これを負わないことは明らかになっています。
一方で、社会的、倫理的な責任に関しては、結果として和解金を支払っているわけですから、こうした責任はあったと解されることが妥当でしょう。
生み出した影響
この事案では、社会で行動する企業、そして規制当局である国や地方自治体に対し、多くの課題を残しました。
まず、化学物質の管理、食品安全規制、公害認定制度のあり方に大きな影響を与えました。規制者は、今回のような事案が今後も起こり得ることを前提に、施策を考えることが求められることとなりました。
一方で、製造者責任の範囲や企業の社会的責任の概念が社会的に問い直される契機となりました。企業はその時点での科学的知見、best available knowledgeの把握に努め、起き得る危険な事態を予見、回避するための最大限の努力が求めらることとなりました。
この点は大学にとっても全く同様です。「研究」という不確実性が高い事業を実施する主体として、起き得る危険な事態を予見し、回避するための最大限の努力が求められることに、企業との差はありません。
不確実性が高い社会的責任
この事案の解決を難しくした最大の要因は、「被害者」の存在であったと感じます。鐘ヶ淵化学に対する法的責任は高裁レベルで否定されています。
そうした中で最高裁は和解への誘導を行いました。民法709条に基づく不法行為責任は、故意または過失がなければ成立しません。「製造段階で危険性を予見できたかどうか」は大きな争点でしたが、下級審での議論はこの点での過失を認めることは難しかったということです。
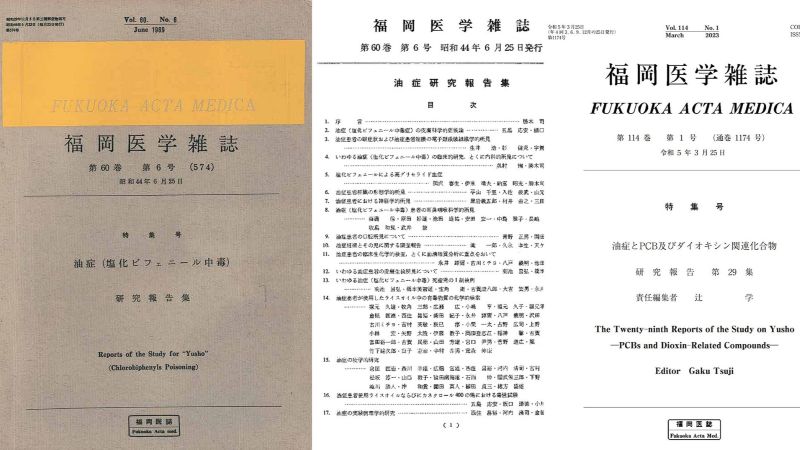
最高裁による和解の提案は、現に被害者が存在する中で、「法的責任を明確に認定」したわけではなく、むしろ長期化した訴訟を整理し、被害者救済を優先する観点からなされたものと理解できます。
その背景には、1970年代は公害事件全般において「企業の社会的責任」への世論の高まりがありました。そうした中、PCB製造者が一切責任を負わないことは社会的に受け入れられにくく、裁判所としては「企業側が一定の金銭を拠出することで早期救済を図る」方向に誘導したわけです。
「社会的」責任というだけに、時の社会の影響を避けることはできないということです。ELSI的視点での検討に際しては、この点に留意が必要でしょう。